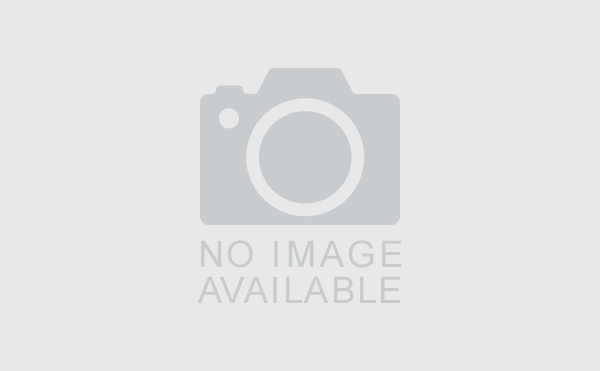日赤発祥と平和への祈り
徳川幕府の時代、世界では欧米列強が奴隷制度や植民地政策を進める中で、アフリカやアジアなどの多くの国々が、その強大な力によって植民地化され、最後に日本もその中に飲み込まれようとしていた。もともと潜在能力が高かった日本。勤勉だった日本人。体制的には朝廷、幕府、各藩。精神的には神道、仏教、そして武士道。それに伴う学問、教育、伝統文化、農業、産業、商い…。いずれも充実していた。日本は自然の要塞である広大な海に囲まれ、成熟した精神的、道徳的文化のなかで、歴史と伝統を継承し、他国からの侵略を防ぎ、裕福とまでは言わないが、有史以来世界で唯一、自己完結で平和な国を保っていた。
この幸せな国民生活に風穴を開けたのが黒船事件である。これが世界の常識かもしれないが、弱肉強食の洗礼でもあった。礼儀も作法もなかった。「礼に始まり礼に終わる」日本の文化とは大きく違っていた。欧米の文明国家は、日本も植民地にしてもよい野蛮な国と決めつけていた。そこには偏見もあった。日本は開国を余儀なくされた。その後、大老井伊直弼が結んだ西洋諸外国との不平等条約。これらに起因する安政の大獄、倒幕運動、下関戦争、薩英戦争、禁門の変、薩長同盟、大政奉還、そして、戊辰戦争等々。これらが明治維新となり、西南戦争の終結を経て、有色人種で唯一、欧米と肩を並べた近代的民主国家が誕生した。坂本龍馬や榎本武揚が国際法を重んじていたのも、こうした日本の将来を目指していたからだ。そこにはトーマス・ブレーク・グラバーなどの西洋人が命をかけて惚れ込むほどの武士道があった。しかし多くのサムライの命が失われていった。世界の先進国と対等に付き合うために、日本に欠けていたものは何だったのか。差し当たり対外的には海軍の創設、国内的には民主化と殖産興業、鉄道の整備だった。もともと海洋国で勤勉な日本人はすぐに追いつくことができた。応用力もあった。しかし、国際基準に追いつくために、もうひとつ日本に欠けていたものがあった。それは「人道」を旨とする、人の命の大切さを重んじた国際ルールへの参加だった。いわゆる赤十字が作ったジュネーブ条約への加盟であり、国内での赤十字社の創設、そのための救護団体の設立であった。それは、国際社会や欧米列強への仲間入りという、日本や日本人に係わる問題でもあった。振り返ってみると、佐野常民は、近代的な国際社会の中で、日本に欠けている諸々の事象全てに全力で立ち向い、自らも知行合一を実践し、みごとに日本をけん引していった。西洋医学の習得、蒸気船や蒸気機関車の製造、海軍の創設、西洋式燈台の建設、国内外での博覧会の実施、日本赤十字社の創設、日本美術の保護など、いくつもの業績を残した。隠れた偉大な人物と言わざるを得ない。
スイス人であるアンリー・デュナンという1人の青年が、国際赤十字を興したときと同じように、西南戦争の最中、佐野常民という1人の男が、激しい国際競争や異文化の衝突の中を生き抜きながら、国家や国民のために必死になって博愛精神を訴え、日本における赤十字を誕生させた。それは皇室や日本国民、儒教や仏教の道徳的精神であり、神道や武士道などと等しく、日本人の得意とするところであった。人類のための国際平和にも繋がっていた。薩摩軍を代表とする旧士族と政府軍との戦いは、お互いが日本の将来を考えた末の戦いだった。戦況は不安定で激しさを増し、死傷者も増え続けていった。どちらが勝つか分からなかった。そうした中で、佐野常民立案の国際ルールを参考にした救護団体の設立と活動は、明治政府から全く受け入れられなかった。軍部の要人も博愛社設立に反対した。「敵味方の区別なく救護する」という考え方が、理解されなかった訳ではない。善美なことと分かったうえでの反対だった。しかも国際赤十字やジュネーブ条約の仕組みを知ったうえでの不許可だった。実際、戦の真最中であり薩摩軍との事前の取り決めはおろか、政府軍内の周知も難しかった。軍とともに行動することや、王師に反する賊徒を救護することも容易なことではなく、混乱を招くのは必至だった。しかし、佐野常民は諦めなかった。最後まで自分の信念を貫き、許可を求め、更には博愛社々則第四条の「敵人の傷者ト雖モ救ヒ得ヘキ者ハコレヲ収ムヘシ」を削除しようとしなかった。その中で、砲弾、銃撃、白兵戦というあまりにも悲惨な多数の死傷者を前に、直裁という形で、博愛社創立が現地熊本城内の征討総督(熊本洋学校教師館ジェーンズ邸)で許可された。命令を下したのは、佐野常民が直接拝謁した征討総督有栖川宮熾仁親王殿下であり、明治政府も後に不許可を取り消し追認した。後押しをしてくれたのは皇室であり、影の協力者は右大臣岩倉具視であった。共に博愛社設立に携わった元老院議官大給恒を筆頭に、松平信正、松平乗承、櫻井忠興、松平乗命、大給近道といった旧藩主等の協力も大きかった。しかしそれは博愛精神からくる日本国民の純粋な願いでもあった。
結果的には、日本人が誰しも持っている「思いやりの心」が、「田原坂」という西南戦争の戦場に糾合され、人道を旨とする「博愛社」という救護団体が誕生した。国が認める唯一の救護団体として世界的な赤十字を目指している。多くの尊い命が散って行く中で、そこで必死に繰り広げられた近代的で国際的な善意の人道的行動。苦しむ人を敵味方の区別なく救護するという赤十字の精神。それが次第に根付き、後に日本赤十字社の事業として引き継がれ、国家を補完する形で幾多の戦争や災害で実践され、現在も赤十字運動として続けられている。これは貴重な歴史であり、これからも育んでいかなければならない。
現在、私たちが生きる21世紀の社会は、インターネットの発達と情報化・デジタル化により大きく変容した。その一方で、大規模災害・疾病・飢餓・紛争・テロ・環境問題など地球規模の課題が目前にあり、混沌とした状況にある。一人ひとり生きる国や環境は違っていても、生命の大切さと平和の尊さを知り、互いに理解し合い、認め合い、助け合う心を持つ。苦しんでいる人がいれば手を差し延べ、その苦しみや痛みを和らげる。人を人として思いやる心。それは、150年前から脈々と生き続ける赤十字の基本原則であり、「人道」の精神の根幹といえる。一人でも多くの「かけがえのない生命」を救うため、私たちは国際赤十字の一員として世界に広がるネットワークで、国の内外で「人道」の原則を実現するために行動している。
ここに、誰もが赤十字の起こりに親しみを持ち、このホームページが、地元の伝承と共に永遠に語り継がれることを願っている。そしてそれが、人の命と健康を大切にし、国内外で発生する人道的被害者に対する博愛無偏の行動となり、赤十字の理想とする戦争のない平和への祈りとなれば幸いである。(梶山哲男)