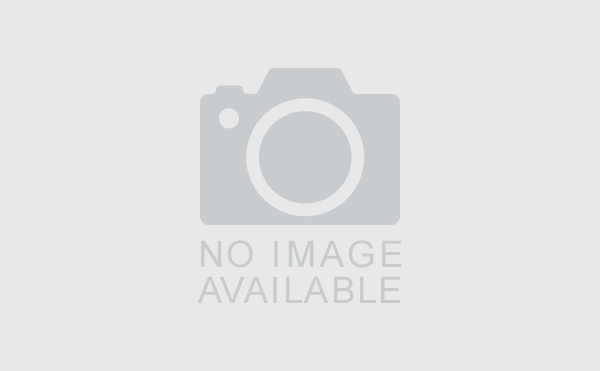「赤十字の起こり」と「人道的使命」
赤十字は、スイス人の青年実業家アンリー・デュナンにより設立された。
デュナンは1859年、イタリア統一戦争の「ソルフェリーノの戦い」に遭遇し、その時の悲惨な戦場と救護活動の体験を「ソルフェリーノの思い出」という一冊の本にまとめた。その中で、デュナンは、「傷ついた兵士は、もはや兵士ではない、人間である。人間同士として、その尊い生命は救わなければならない。」と訴え、「戦場の負傷者と病人は敵味方の差別なく救護すること」、「そのための救護団体を平時から各国に組織すること」、「この目的のために国際的な条約を締結すること」などを提案した。彼の提案は反響を呼び、1863年、スイス人による5人委員会(後の赤十字国際委員会)が結成され赤十字が誕生した。そしてジュネーブ条約(国際人道法)が作成され、これに批准(加盟)した国には、「政府から救護団体として認められること」、「一国一社であること」を条件に、後の赤十字原則(人道、公平、公平、中立、独立、奉仕、世界性)を旨とする民間の人道的救護団体としての赤十字社が設立されていった。
一方、日本の赤十字は、元老院議官(げんろういんぎかん)佐野常民(さのつねたみ)らによって創立された。
佐野常民は、パリ(1867年)やウィーン(1873年)で開催された万国博覧会の団長として参加したとき、そこに出展されていた赤十字パビリオンで、赤十字の重要性やその広がりを目の当たりにした。そして、日本での設立とジュネーブ条約の加盟を願うようになっていた。近代的国際国家を目指す明治政府の要人や軍部の中にも、その重要性を理解している者もいた。そしてそのきっかけが、なかなかつかめないでいるなか、1877(明治10)年2月に西南戦争が勃発した。戦火は日増しに激しくなり、死傷者も増え続けた。皇室は自ら包帯等をお作りになり負傷者にお配りになった。それに感激した太政官三条実美と右大臣岩倉具視は、赤十字を知りながらも、あえてクリミア戦争でのナイチンゲールの救護活動を例に挙げ、華族らに寄付金や救援活動を行うよう働きかけた。元老院議官大給恒(おぎゅうゆずる)は欧州貴族会のような一般市民のための病院開設を申し出た。佐野常民はもちろん、アンリー・デュナンの思いと同じ人道的救護団体の設立を願った。そして、田原坂を中心とした地域で激しい戦闘が続く中、岩倉具視の仲介で佐野常民と大給恒が博愛社創立を立案した。「博愛社創立請願書」には、デュナンの著した「ソルフェリーノの思い出」と同様に、戦争の悲惨さや、負傷兵を人道的に見捨てられないことが記載され、欧州の例や、皇室の思いと博愛精神が説かれている。また、請願書に添付された「博愛社々則」には、欧州各国の赤十字社を模範とした救護団体の組織運営が提案されている。その願いは激しい戦火の中、なかなか認められなかった。誇り高き武士にとって無用なものであった。博愛社創立を急いだ佐野常民は、明治政府に博愛社創業のための移動日を除く50日間の休暇願を申請し、政府の出張命令を得て、戦地で直接征討総督有栖川宮熾仁親王殿下に申請することとなった。そのとき政府軍の征討総督本営は、城北(高瀬)から熊本城内の熊本洋学校教師ジェーンズ邸に移動していた。征討総督有栖川宮熾仁親王殿下は、銃撃戦によるあまりにひどい惨状と、多くの戦傷者の悲惨さに心を痛めておられた。殿下は総督本営で佐野常民の申請を受け即刻、日本赤十字社の前身である「博愛社」の創立認可の命令を下された。その時、殿下に拝謁した佐野常民は、感極まって号泣したと云われている。博愛社の創立は、目の前の戦傷病者を敵味方なく救うと同時に、近代国家としての日本を見据えた人道的救護活動であり、人道・博愛精神による奉仕や寄付金を基盤とする国民運動でもあった。
佐野常民は、ウィーン万国博覧会の感想から、「文明といい開化といえば、人みな、すぐに法律の完備や器械の精巧等をもって、その証と言うけれど、余は独り赤十字社のかくの如き盛大になることをもって、文明の証としたい。真正の文明は道徳的行動の進歩が伴わなければならない、…」と訴えていた。また、博愛社の創立請願書には「山野に委(ゆだね)し、雨露に暴して、死を待つといえども、捨て顧(かえり)みざるは人情の忍ばざる所に付、是また収養救治いたし度、御許可有之候…。」と、17昼夜におよぶ「田原坂の激戦」の悲惨な戦場を描いた記述があり、さらには皇室の精神や、欧州の人道的な戦時救護を例に挙げ、「本件の義は一日の遅速も幾多の人命に干し即決急施を要し候…。」とある。そしてそれは、多くの国民の願いでもあった。国際赤十字が「ソルフェリーノの戦い」をきっかけとして誕生した時と同じように、日本では西南戦争の「田原坂の戦い」をきっかけとして、ついに皇室の保護のもとに、1877年5月に戦地熊本で「博愛社」として誕生した。そして、日本がジュネーブ条約に加盟した翌年の1887年に、日本赤十字社と改称し現在に至っている。佐野常民が、「熊本こそ 此れ 赤十字事業の 創業の地なれ」と言っているとおり、西南戦争の戦場において、日本における近代的な人道的行動と赤十字運動が開始された。また、それが現在へと、世界へと繋がっている。その歴史的意義は大変大きいものと言わざるを得ない。イタリアのソルフェリーノの丘に近いカスティリオーネの教会で、婦人達が必死の救護活動を行ったように、熊本の田原坂に近い植木町、玉東町、亀井町、玉名市及びその他の周辺地域のお寺や町医者などにより、献身的な救護活動が行われていた。それは熊本から九州、そして日本全土に広がり、その延長線上で日本の赤十字が誕生した。
日本赤十字社の起こりは、明治期最大で最後の内戦である西南戦争にさかのぼることができる。そのときの激戦地が日本赤十字社の前身である博愛社を誕生させた。つまり、西南戦争の戦場こそが日赤を誕生させたことになる。それが、田原坂及びその周辺地域が「日赤発祥の地」と言われる由縁でもある。そして、その活動は、我が国における近代的(世界的)な人道的行動の歴史的第一歩となった。私たちは、イタリアのソルフェリーノの丘と同じように、官軍及び薩軍の戦死者約14,000人の名前が刻まれている田原坂の「西南役戦没者慰霊之碑」や、「田原坂崇烈碑(熾仁親王撰文竝篆額)」を前にして、これまでの幾多の戦争や災害で犠牲となった多くの御霊に心を寄せ、赤十字の誕生に想いを起こすことができる。そして、「被害者の人道的利益を守るためにはどうすべきか」という、赤十字の黄金律を常に自問自答しながら、赤十字の理想とする人道的任務を達成し、赤十字の人道的使命を具現化していかなければならない。
人々の命と健康を守り、赤十字の理想とする戦争のない平和を願って。
(日赤発祥の地研究会 梶山哲男)